相続人の範囲と法定相続分を確認する
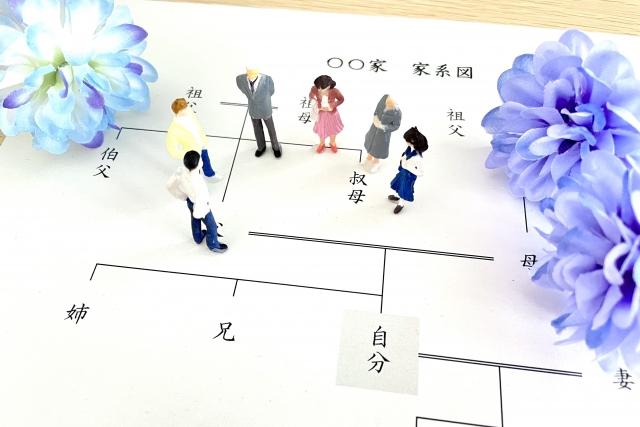
相続人の範囲と法定相続分
- 配偶者
- 【常に相続人】
【法定相続分】
子どもがいる場合は1/2、子無し・親ありの場合は2/3、子も親もいない場合は3/4
- 息子・娘・孫
- 【第1順位】
被相続人の子どもが第1順位となります。こどもが死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫が相続人となります。
【法定相続分】
1/2 (子が複数いる場合は等分)
- 父・母
- 【第2順位】
被相続人の子どもが死亡している場合、あるいは被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の父母が相続となります。
【法定相続分】
1/3 (直系尊属の親が複数いる場合は等分)
- 兄・弟・姉・妹・甥・姪
- 【第3順位】
被相続人に子どもと父母がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹がいない・死亡の場合は、甥・姪が相続人になります。
【法定相続分】
1/4 (兄弟が複数いる場合は等分)
法定相続人は範囲と順位が決まっている
法定相続人になれるのは、基本的に配偶者・親・子ども・兄弟姉妹で順位が決まっています。この時、第1順位の子どもが健在なら、第2・第3順位の人は相続人になれません。
内縁の妻・夫の処遇
原則として、内縁の妻と夫は相続人にはなれません。但し、相続人が1人もいない場合は「特別縁故者」として相続財産分与を家庭裁判所に申し立てることができます。審判で申し立てが認められれば財産分与を受けることができます。
相続関係を戸籍で確認する
戸籍謄本
戸籍簿の写し。戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する証明書。夫婦と未婚の子どもによつて構成されます。
戸籍妙本
戸籍簿の写し。戸籍謄本が世帯全員分の証明書であるのに対して、戸籍妙本は戸籍に記載されている一個人の証明書となります。
改正原戸籍謄本
昭和22年と平成6年7の法改正で戸籍を新しく作り替えた際に元となった戸籍のことを「改正原戸籍謄本」といいます。
除籍謄本
結婚や死亡などで記載されていたすべての人がいなくなってしまった戸籍のこと。そういう戸籍は戸籍簿から除外されるので「除籍」といいます。
配偶者は常に相続人 次に優先されるのが子ども
民法では、相続することができる人物を「法定相続人(相続人)」として、その権利と範囲を定めています。相続人の資格があるのは身内だけで、その順位と相続の割合(法定相続分)は決まっています。この中でもっとも優先されるのは配偶者です。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の身内には順位がつけられます。配偶者に続き第1順位として優先されるのが被相続人(故人)の子どもです。子どもが死亡している場合は、その子ども(被相続人の孫)が相続人となります。なお、子どもの配偶者は、被相続人が亡くなったあと、遺産分割協議が終わる前に相続人となっている子どもが亡くなった場合を除き、相続人になることができません。被相続人に子どもがいない場合は第2順位となる父母が相続人になります。また、父母もすでに死亡している場合は祖父母が相続人になります。子どもも父母がいない場合は、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が、兄弟姉妹も死亡している場合は、その子ども(被相続人の甥・姪)が相続人になります。

戸籍謄本の取り寄せは専門家に頼る方法もある
相続人を特定する場合は、安易に決めず、まずは非相続人の戸籍を調べましょう。場合によっては家族の知らない離婚歴や子ども・養子がいる場合もあります。また、相続人に預貯金の名義を変更する際、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える必要があるため、いずれにしろ戸籍謄本を入手しておく必要があります。戸籍謄本には、両親や兄弟姉妹ついて、誰と結婚し何人の子どもがいるかが、すべて記録されています。戸籍謄本さえみれば、すべての相続人とその順位を確認することができます。また、故人の本籍地が結婚などで変更されている場合、戸籍すべてを確認するためには、死亡時の本籍地から出生時の本籍地までさかのぼって戸籍謄本を請求する必要があります。この作業は非常に労力がかかるので、行政書士や司法書士などの力を借りることも検討しましょう。

